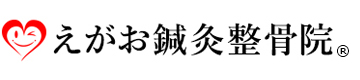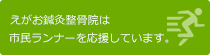私たちにとって「睡眠」は、心と体の疲れをとる大切な時間です。しかし、「寝つきが悪い」「夜中に何度も起きる」「朝スッキリしない」など、睡眠に関する悩みを抱える方はとても多くなっています。 現代医学では、ストレスやホルモンの乱れ、自律神経の問題などが原因として挙げられますが、東洋医学では「気・血・水(き・けつ・すい)」や「五臓(ごぞう)」のバランスの乱れが深く関係していると考えられています。 東洋医学で見る〔眠り〕のしくみ 東洋医学では、体と心の健康は「陰陽のバランス」によって保たれていると考えられます。 •日中は「陽」:活動的で外向きのエネルギー •夜は「陰」:休息・回復のエネルギー つまり、夜になると「陰」が優位になり、体も自然と眠りのモードに入っていくのが理想です。しかし、ストレスや体の不調によってこの「陰陽のバランス」が崩れると、眠れなくなってしまうのです。 こんなタイプの不眠に要注意! 1.心(しん)】が乱れているタイプ 心は「精神・意識」を司る臓腑で、睡眠と直結しています。ストレス・不安・過労が続くと、心が興奮し「眠れない」「夢を多く見る」「途中で目が覚める」といった不眠が起きやすくなります。 2.【肝(かん)】の不調によるタイプ 肝は「気・血の流れ」と深く関係し、ストレスの影響を受けやすい臓腑。イライラしやすく、夜になると頭が冴えてしまう方はこのタイプかも。 3.【腎(じん)】が弱っているタイプ 腎は「生命力の源」加齢や過労によって腎の力が落ちると、浅い眠りや早朝覚醒などが起こりやすくなります。中高年に多い傾向です。 ◇東洋医学的・睡眠改善のポイント 1.ツボ刺激(鍼灸・指圧) →心・肝・腎のバランスを整えるツボ(神門、太衝、失眠など)への刺激で、自然な眠りをサポートします。 2.お灸・温活 →冷えは「陰の働き」を妨げます。お腹や足元を温めることでリラックス効果が高まり、眠りに入りやすくなります。 3.漢方や食事療法 →体質に合わせた漢方や、夜に体を冷やさない食事で体の内側から睡眠の質を整えます。 ◯まとめ 眠れないのは、心や体の不調の“サイン”かもしれません。東洋医学では「症状だけでなく体全体のバランス」を見ることで、根本から睡眠トラブルを整えることができます。 薬に頼らず自然な眠りを手に入れたい方、眠りの質に悩んでいる方は、ぜひ一度、東洋医学的な視点で自分の体と向き合ってみてはいかがでしょうか